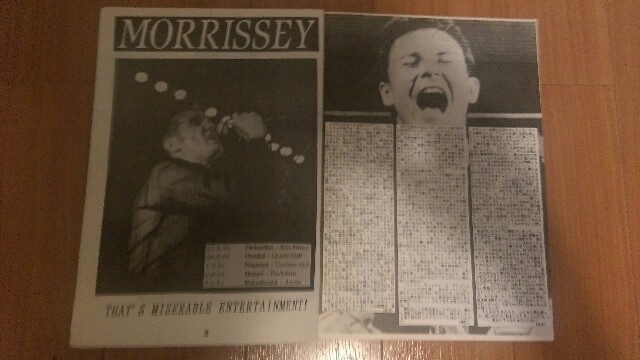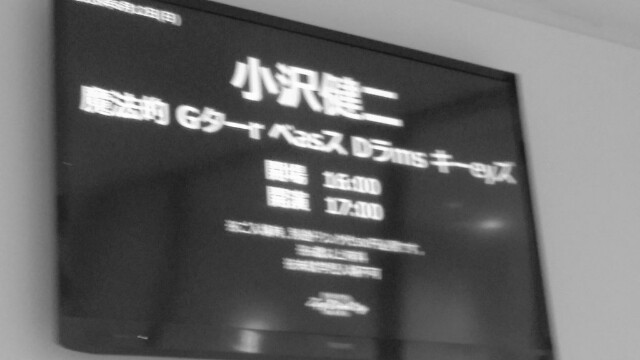90年代はアルバムより12インチ・シングル、しかもリミックス盤ではなく、4曲入りミニ・アルバム的なものが好きだった。さらに遊びでDJをやっていて、60~70年代のジャズ、ソウル、ブラジルの中古盤を漁っていたので、時代感覚がかなり麻痺している。でも、90年代邦楽アルバム・ベスト20をやったのだから、洋楽をやらないわけにはいかないけど、20枚だとかえって絞りきれないから潔く10枚にしよう…と、ベスト○○を書く時、人はなぜ言い訳がましくなるのだろう。
●Screamadelica / Primal Scream
90年代マンチェ・アンセムのCome Together がシングル・ヴァージョンではなくリミックスだったり、タイトル曲が後にリリースされた12インチ・シングルに収録されたりだが、それもご愛嬌と思えるボビーのぶっ飛び音楽快楽主義者ぶりが全開のアルバム。
●Loveless / My Bloody Valentine
耽美なノイズと快活なリズムの融合。1991年の来日ライヴで客出しにプライマルのCome Togetherを選んだぐらい、当時ケヴィンがいかにプライマルに影響を受けていたかがわかるアルバム。
●The Comforts of Madness /Pale Saints
90年代前半は、雨の後の筍のようにイギリス・インディ・シーンに轟音ノイズ・ギター・バンドが登場したが、その中で一番好きだったバンドの1st。残念ながら2nd以降は好きになれなかった。
●The La's / The La's
ネオアコの名盤とされるが、マージービートの再来だと個人的には思う。2005年のサマソニ大阪公演でアンコールでフーのMy Generation をやったのに、東京公演(場所は千葉だが)ではやらなかったことの怨みを関東人は忘れない。
●The Return of Space Cowboy / Jamiroquai
ブランニューヘヴィーズもガリアーノもコーデュロイもスノーボーイも好きなのはアルバムではなく12インチなので、ジャミロクワイを選んだ。因みに今でもJ.K. 以外のメンバーの名前は知らないし、しょっちゅうメンバー・チェンジするので覚える気もない。
●Supernatural / Misty Oldland
高身長でモデルもこなす美人だったのに、109のギャルには支持されなかった。
●Walking Wounded / Everything But The Girl
ドラムンベースはいろいろ聴いたが、結局好きになれたのはこのアルバムだけだった。
●Protection / Massive Attack
リリース当時、このアルバムとフィッシュマンズの『空中キャンプ』ばかり聴いていた。ライヴは初来日、フジ、サマソニと三回も見ているが、いずれも印象が良くないのは、ゲストにトレイシー・ソーンを連れてきてProtectionをやらないから(無理なのはわかっているが)。
●Vanessa Paradis / Vanessa Paradis
レニー・クラヴィッツの最高傑作は自身のアルバムではなく、このプロデュース作品だと思う。
●Be Gentle with My Heart / Roger Nichols And A Circle of Friends
内容はあまり良くない日本独自企画のアルバムだが、ロジャー・ニコルスの素晴らしさを発見したのは日本人だし、こういうアルバムが最新のアルバムと一緒に売られていたのが90年代の面白さだったと思う。
以上、結局あれも選びたい、これも選びたい、と悩んだが、やっぱり90年代楽しかったよね、ということで。